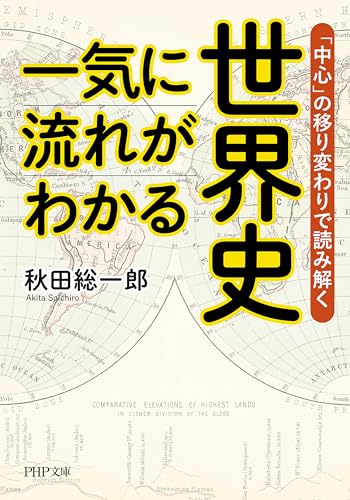つい先日、noteに新しい記事を投稿しました。過去数千年にわたる、各年代の「世界で最も大きな(最大級の)都市の人口規模」を片対数の目盛りに落としたグラフについて。「最大級の都市の変遷グラフ」と名づけました。
この記事は、私にとっては「20年かけて書いた」ともいえる、とくに重要なものです。ぜひお読みいただければ。
グラフはつぎのようなものです。ここには、メソポタミア文明のウルク、バビロン、ローマ、唐の長安、バグダード、ロンドン、ニューヨーク等々の、各時代を代表する歴史的な都市のデータが落とし込まれています。詳しい説明は、リンクのnote記事をご覧ください。

なぜこのようなグラフを描いたのか。「世界史において、進歩・変化の速度が時代によってどのような変遷をたどったか」を可視化するためです。グラフは、さまざまな変化の過程を可視化するための代表的な表現方法です。
「世界史の各時代において、進歩や変化の速度がどうだったか」ということは、世界史の概説や入門的な話のなかでは、めったに取り上げられません。しかし、本来は重要な事柄だと思っています。
***
このグラフは、つぎの前提に立っています。
・最大級の都市の人口規模は、その時代の技術や社会運営の能力によって制約を受けている。
・そこで、最大級の都市の規模が急速に大きくなっている時期(グラフは急勾配の右肩上がり)は、技術革新が盛んな時期であり、規模拡大が停滞していれば(グラフの傾きはゆるやか、または平坦)、それは技術革新などの停滞を示している。
・つまり、各時代を代表する最大級の都市の規模は、その時代の文明が到達した技術や生産力の総合的な水準を示している。
***
「進歩・変化の推移を示す数量的指標であれば、世界の人口やGDPの数千年の移り変わりをたどればいいのでは」と思う人もいるかもしれません。
しかし、世界の人口やGDPを数千年間にわたってたどることのできる、信頼のおけるデータは存在しません。
その手の数値を述べた文献もありますが、それはきわめて強引な推定を重ねたものです。それで数千年を追いかけても、その数値を算出した人の世界史像をなぞるだけになります。つまり客観性におおいに問題がある。
しかし、各時代の最大級の都市ならば、大ざっぱではありますが、それなりの客観的な推定が可能なのです。紀元前の都市であっても、遺跡調査から面積や建造物の状況などがわかるので、そこからある程度人口を推定できたりする。
私は、いろんな専門家・歴史家の本から、さまざまな時代の都市についての情報を拾って、このグラフを描きました。
そして、このような「最大級の都市の変遷」グラフを描くと、世界史についての一般的なイメ―ジとは異なるストーリーが浮かび上がってきます。
よくあるイメージは「古代・中世は進歩がゆっくりで、近代になって加速し、近年はさらに加速」というものでしょう。グラフ的に描けば、つぎのような感じ。

しかし、それはちがうのではないか、じつは、世界はこの数千年で数百年単位の長期的な加速と減速をくり返してきたのではないか。グラフ的に描けば、つぎのような階段状の発展、あるいは複数のS字曲線がつながったイメージです。

***
以上のような考え方に基づくグラフを描くことや関連する世界史についての議論を、私は20年ほど前から続けていて、長文のレポート(グラフ含む)を私的な研究会で発表したり、以前にやっていたブログに記事をアップしたりしてきました。
世界史における加速・減速という視点であれば、1990年代末からのテーマで、2000年代初頭にやはり長文のレポートを書いて、仲間内で発表しています。
しかし、どれもいろいろと至らない点があって、読んだ人から思わしい反応を得るのはむずかしかったです。読んでもらうこと自体、むずかしかった(ありがたい例外もありましたが)。
ただし、このような「加速と減速の世界史」を追究するなかで、スピンアウト的に、私の著書(秋田総一郎『一気に流れがわかる世界史』PHP文庫)も生まれたのでした。
***
今回は、長年のテーマを、かなりの手ごたえでまとめることができたと思っています。この記事を書くために、背景的なことも含め、相当な時間をかけてきました。
そして、日本語の文献しか知りませんが、私のような問題意識や考え方に基づいて、この記事のようなグラフや議論を打ち出している人は、どうも見当たらない……少なくとも私くらいに熱心に追及している人は見当たらないようだ……
そう言うと、素人・アマチュアの思い込みや誇大妄想と思われそうです。まあ、アマチュアによる世界史の大風呂敷な議論の「これはちょっと…」という感じのものを私もみてきましたので、そう思われても仕方ないとも思います。
でも、それなりにこのテーマについて調べたり考えたりしてきたので、「思い込み」でもないのでは、という自信もあります。
この記事は、世界史や歴史が好きだという人にかぎらず、むしろ理系の方にとってのほうが読みやすいところもあるかもしれません。
2万文字余りの非常に長い記事ですが、最初の数千文字(全体の3分の1)でだいたいの内容はわかります。
正月に読書したいという方、その読書の予定に、この記事もぜひ加えていただければ。世界史についての新しい見方を提供できると自負しています。
私は、やはりこういう大風呂敷な世界史の話が一番好きですね。自分の「本業」だと思います。取り組んでいると、幸せとワクワクを確かに感じます。来年(2026年)はもっとこのテーマに時間を割きたいと思っております。
(以上)