負け犬が絶妙などんでん返しにエクスタシーを覚えた件「恐怖」
世間でも、ほぼ誰にも知られていない。そんなどんでん返しを発掘する喜びに打ち震えること請け合いの大良作
(評価 80点)

どんでん返し。この言葉に胸をときめかさない映画ジャンキーなんているのだろうか?
そもそも、作り話のフィクションには、どんでん返しという返し技が存在する。
読み手や観客が、当然そうなるべきであろうという意識下で行っている想定を、いつの間にか覆してしまうという、作り手側のそんな企みにまんまとはまらされてしまう決め技の事だ。
受け手の騙され方がキレイなほど、一本技が成立するし、騙された受け手の方も、技がキレイに決められれば決められるほどカタルシスを覚えてしまう。当然、どんでん返し映画なるジャンルもあるわけで、いくつものタイトルを思い浮かべる方も多いはず。

でも、聞き飽きたような(たとえばシックスセンスとか・・)作品ばかりで、結局、貪欲な観客である我々は、常に斬新などんでん返しを求め、日夜、キレイに騙されることを心のどこかで熱望している。
世間でもそれを知っているから、特に小説など、どんでん返しを謳って、帯の惹句にデカデカと掲げているものも多い。でも、そんなものに限って、どんでん返しを意識的に狙って、やたらとツイストばかりを仕掛けて逆に白けてうんざりさせられるものも多い。

つまり、フィクションにおけるどんでん返しとはそれほど高等な技なのだということ。
決まり切ったシンプルな道具立てと、数少ないキャラクターだけを操って如何にラストの驚きに導くか、そんな小気味の良い驚きを誰もが望んでいるものなのだ。
しかし、そんなサプライズもほぼ出尽くしたかと、嘆いていた矢先、思わぬ伏兵が意外な所から現れて、大いに驚嘆させてくれた。
それこそが、50~60年代にB級ホラーのプログラムピクチャーを量産していたハマープロが生み出した最高傑作といってもいい、本作「恐怖」なのだ。

ハマープロといえば、ドラキュラやフランケンシュタイン、それに狼男を筆頭にした低予算のホラー映画を誰もが思い浮かべるはず。
この負け犬も、ハマー映画と言えば、そんな安っぽい印象しかなかった。
だから1961年製作の、そのものズバリの「恐怖」と銘打たれた本作も、半ばたかをくくって、見始めたと言っていい。
ところが、本作は、そんな負け犬の侮りを見事なまでに覆してくれた。

冒頭、湖で若い女性の水死体が引き揚げられるタイトルバックで幕を開ける本作。
映画はそこから、主人公のペニー(スーザン・ストラスバーグ)が、10年間会っていなかった父親に会うため、南仏のニースの別荘にやって来るところからはじまる。
別荘でペニーを出迎えた後妻のジェーンは、父親は仕事の用事で不在だと告げるのだが。
主人公のペニーは落馬事故で下半身不随の車椅子の生活。そんなペニーは、夜中、不審な物音で目を覚ますと、音に導かれるように入ったサマーハウスで目を見開いた父親の姿を見かけ叫び声をあげる。

父親を見たというペニーに、後妻のジェーンも運転手のロバートも、かかりつけの医師も耳を貸さず、次第に追い詰められていくペニー・・とくれば、典型的なニューロティック・スリラーの定石。この手のスリラーなら、ハマーをはじめ、誰もが見ているはず。
おそらく、父親の財産を狙って、車椅子生活のペニーに良からぬ企みが仕掛けられている、と誰もがそう思う。加えてかかりつけの医師を演ずるのがドラキュラ役者のクリストファー・リーとくれば、その後の展開は、こうなるはずだと、大抵の人は脳の中で決めてかかってしまうはずだ。
実際、そうなのだ。実際、本作も、プロットは、定石通りの定番なのだ。
しかし、本作はその定番の中に、実に巧みなツイストを効かせて我々を小気味よく驚かせてくれる。
人間の脳には、それまでに見た話の展開が無意識のうちに植えつけられる、刷り込みという現象が起きている。
それが、刷り込み通りに展開することで、カタルシスをもたらすのが、人が飽きずに映画を見たり、小説を読み続ける、一つのメカニズムとも言っていい。
しかし、その刷り込みのスキをついて騙されるカタルシスの方が実は数倍も大きい。
それこそがどんでん返しの醍醐味なのだ。
映画を見ている間中、ずっと疑問符が浮かびっぱなしの冒頭の伏線が見事に回収されるラストでもたらされる騙されたという快楽と、思わず快哉をあげたくなるようなカタルシスを備えた、掘り出し物の本作。どんでん返しに餓えたあなたにぴったりの作品であることは請け合いですよ
負け犬が思わぬ掘り出し物でセブンティーズを満喫してナイスな気分になった件「アイズ」
セブンティーズの空気感とサイケでジャッロな殺人劇が見事にマッチしたこれこそ掘り出し物の良作サスペンス!
(評価 78点)
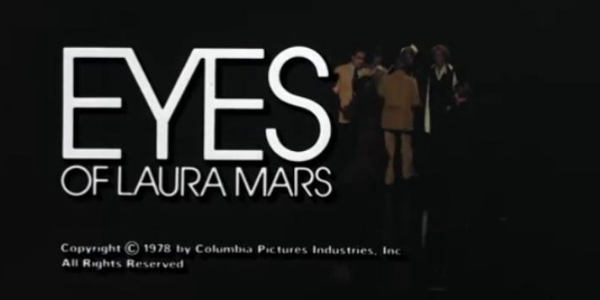
負け犬ほどのシニアな映画フリークなら、誰でもゴールデンな黄金時代というこだわりの年代があるのではなかろうか。そのゴールデンエイジこそ、まさにアメリカ映画が鋭角な切り口で華開いた70年代。
序章ともいうべき「フレンチコネクション」を筆頭に、「タクシードライバー」や「狼たちの午後」など、唯一無二なその時代の名作を挙げだしたらキリがない。
そして、主に当時のニューヨークを舞台にした、そうした作品に共通するのが、エッジの効いた空気感。ハイパーリアリズムのような、ザラザラとした質感を思わせるルックスだった。

かくして、本作の「アイズ」。製作は70年代の末尾の1978年。「JAWS」を端的な例として、当時、映画のビジュアルイメージが映画ポスターでほぼ決定づけられていた時代、ポスターの全面を占める主演のフェイ・ダナウェイの顔のクローズアップに、真っ白な三白眼を晒したインパクトのあるイメージが映画雑誌に載っていて、まさに目を奪われてもいた。
だが、高名な女流写真家が、サイキックな霊視能力で、殺人現場をリアルタイムで霊視出来るようになって・・云々のB級っぽい紹介記事と、当時のどっちつかずの曖昧な映画評を見て、勝手に駄作と決め込んで、フェイ・ダナウェイがそのトレードマークの美脚を顕わにしてキャメラを構える決めのビジュアルは脳裏に刻み込まれながらも、結局、今の今まで、見る事もなく年月が過ぎ去っていた。

以来、幾年月、急に、その「アイズ」の脚本があのジョン・カーペンターだったのを思い出したことをきっかけに、懐古趣味もあいまってようやく見た本作。何のことはない、これが掘り出し物の良作ですっかり嬉しくなった次第。
開巻は、いきなりの主観ショットが繰り出される霊視による殺人シーン。この自らのサイキックな能力に慄きながら事件に巻き込まれるのがフェイ・ダナウェイ演ずる写真家ローラ・マーズなのだ。

ファースト・シーンから歴然なように、本作の基本コンセプトは、イタリアで隆盛を誇ったスラッシャーな殺人シーンが売りの通称ジャッロ映画のアメリカナイズ。これなど、自身映画マニアなジョン・カーペンターならではといったところ。
しかし、本作ではイタリアンでグロな殺人描写はまずなく、それに取って代わるのが、ローラを取り巻くファッション写真業界のビジュアライズと、それを彩る70年代のイカすディスコ・ミュージックの数々。
とりわけ、何よりもこの負け犬のアンテナにずばり刺さったのが、ローラの作品群のリソースの写真に、あの巨匠ヘルムート・ニュートンの作品群が惜しむことなく使われていることだった。
ニュートンといえば、カミソリのような目の覚めるような切り口で被写体を切ってのけるエロスの巨匠だが、本作の、エロスと暴力という作品テーマを売りにファッション写真業界で時の人となるローラ・マーズというキャラクター設定に、これ以上ピッタリな逸材はいない。
この負け犬も若い頃からニュートンの作品群には心酔していて、写真集も何冊も持っている。

フェイ・ダナウェイとヘルムート・ニュートン。しかし、よくもまあ、こんなゴージャスなカップリングが実現したなと思う間もなく、つぎつぎとアクテイブにセブンティーズのルックスと、実際のヘルムート・ニュートンの作品の撮影現場の再現を思わせるシーンがディスコ・ミュージックの軽快なテンポそのものに繰り出され、あれよあれよと引きづりこまれていく。
ローラを取り巻くバイプレイヤーも、トミー・リー・ジョーンズにブラッド・ドゥーリフ、それにラルフ・ジュリアと、その時代に異彩を放った嬉しくなるような曲者ばかり、とくれば、もう二転三転して犯人が、ジャッロ映画の定石通り明かされるラストまで目が放せなくなってくる。

そもそも、本作に手が及ばなかったのも、監督が手垢のついたような高齢の職人監督のアーヴィン・カーシュナーだったからなのだけど、本作では、或る意味、職人臭さを臭わせない実にフレッシュでアクティブな演出で目を見張らせてくれる。
ニュートンのビジュアルに、ブラックコーヒーのようなテイストでアメリカナイズされたジャッロ映画のトーン、それにピリピリとした殺伐としたイカすセブンティーズのルックスとディスコミュージックの混然一体とした世界、あなたも是非、いかがでしょうか。

負け犬のような映画フリークからすれば、これが、監督がアーヴィン・カーシュナーではなく、当時、気鋭の映像の魔術師ブライアン・デ・パルマだったなら夢のドリームマッチになったのに・・・などと淡い夢まで見させてくれる憎い存在なのですよね~
負け犬が大空を見上げ夢想していたガキの頃のことを思い出した件「NOPE ノープ」
誰もが空を見上げ、漂う雲に思いを馳せていた子供の頃。そんな子供心の琴線をくすぐるようなセンスオブワンダーを感じさせるスーパーナチュラル・ホラーの快作
(評価 78点)

真っ青な広大な空にポッカリと浮かぶ雲。そのどれ一つとして同じ形はない。それどころか、ある雲はモクモクと、また、ある雲は優雅にたなびいて、まるでパフォーマンスでも披露しているように見える。子供の頃なら誰もが、そんな雲をみながら夢想に耽った時があったのではなかろうか。
本作は、一見、ありふれたサイファイ映画と思わせておいて、誰の心にでもあるセンスオブワンダーな童心をくすぐる、ちょっと意外なアイデアで存分に楽しませてくれるスーパーナチュラル・ホラーの秀作だ。
ジョーダン・ピール。映画好きの人なら、この男の名前、誰もが聞いたことがあるはず。そう、あの人種差別ホラーとして世界中で大ヒットした「ゲットアウト」でブレイクを果たした新進気鋭の監督だ。

負け犬が「ゲットアウト」を見た時、真っ先に想起したのが、あの往年の伝説のTVシリーズ「トワイライト・ゾーン」だった。スピルバーグはもとより、それより一世代、二世代も若い世代でさえ、本国で繰り返し再放送されていたに違いない、超絶的なクォリティーを誇るこの番組に心酔していたクリエイターも多いはず。
続く第二作「アス」を見た時、ジョーダン・ピールもまた「トワイライト・ゾーン」好きの一人に違いない、そんな確信を新たにしたものだ。つまり、ジョーダン・ピールの作品に通じていると直感的に感じたのが、センスオブワンダーなアイデアだった。
「トワイライト・ゾーン」に通念として流れるテーマとは、日常に隣人のように寄り添う、奇妙な物事。この負け犬が「トワイライト・ゾーン」を最初に見たのは、番組名が「ミステリーゾーン」の時だった。毎回、繰り出されるアイデア豊かで、子どもの恐怖心にも訴えかけるセンスオブワンダーなエピソードの数々に夢中になった。
果たして、「ゲットアウト」、「アス」と、二作を立て続けにヒットさせ、一躍、第二のシャマランとして躍り出たそんなジョーダン・ピールが放った第三作目「NOPE ノープ」とはどんな作品なのか?
のっけのオープニングからまず、意表を突かれる。
TVのスタジオのセット、そこに少し興奮気味のチンパンジーがフレームインしてくる。子ども番組のセットのようだ。しかし、そこには横たわる女性の足が椅子の端から突き出ているのが見える。どうやらそのチンパンジーが修羅場と化したセットの張本人らしい。でも、一体、何故、どうして?

「ゲットアウト」、そして「アス」と、ジョーダン・ピールはやはりイントロが上手い。巧みなイントロといえば、TVシリーズが視聴者に訴えかけるのにマストなメソッドだけど、本作のイントロなど、まさにTV世代のジョーダン・ピールの面目躍如といったところ。
そして、うってかわって本編の舞台は、広大な平原が広がる田舎の牧場。牧場を営む一家の二代目、本作の主役でもあるOJがいつものように馬の世話をしていると、空気をつんざく音と共に空から小さなコインが落ちて来る。牧場の経営者でOJの父親のこめかみにそのコインが不運にも貫通し急死を遂げる。
いきなりの不条理な死。牧場を継ぐことになったOJは、やがて上空に拡がる雲に不穏な感情を覚え始め・・・

本作の予告動画やポスター、それにスチールを見た人なら、およそ本作が、未確認飛行物体に関わる映画であることが予想がつくはず。現にこの負け犬も、何の疑いもなくすっかりそう思い込んでいた。
而して、確かに本作、序盤はあのスピルバーグの「未知との遭遇」を今さら、完コピしたようなシーンが続々と現出する。だからといって興ざめすることがないのも、冒頭のTVセットのシーンをはじめ、風に揺られて根が生えたように立ち昇るバルーン・ドールなど、ワイドショットで捉えた拡がりのある映像のクオリティーが高いのと、確信犯的にジャンル映画の定石を踏む、そのスタンスにどこか揺るぎない自信が感じられたから。

その上、映画の進行につれ、ごった煮のように様々な映画のカラーが混在していくのが面白い。ちょっとポンコツな面々が集まって未知の物体に立ち向かうのは「ジョーズ」然り、B級モンスター映画好きなら「トレマーズ」といったところか。
ところが、いよいよ後半に至って、その物体をめぐり、ピールは予想外の正体を提示してくる。この辺り、凡百のジャンル物だとタカをくくっていた負け犬などはホーと嘆息して少し感心した。

その上、イントロが、登場人物が子ども時代に体験したトラウマだったことが明かされ、本作がいわば子供時代のそこはかとない恐怖に根差したサイファイであるという重層的な仕組みを持った作品であることが明かされるに至って、感心が賞賛に変わっていた。
他にもチャプター仕立ての語り口、要所でイカすRBの曲の数々でアクセントをつけるタランティーノ映画を思わせるテイストなど、本作の魅力は尽きない。

表面的なアイデアのみに固執するシャマランとは違う、一作ごとにテーマの切り口を変えて来るこのジョーダン・ピールという新たなダーク・ホースの動向、馬好きならずとも見逃す手はなさそうですよ~
負け犬が恐るべき子供たちに共鳴し感応し戦慄した件「イノセンツ」
能力は共鳴し覚醒する!ノルウエー発の静かなるサイキックホラーの傑作
(評価 80点)

澄み切ったどこまでも静かなる空気。冷え切った風景の中に屹立する高層団地のシルエット。そんな、どこまでも静かな空間で子供たちが遊んでいる。何処にでもある、ありふれた光景。でも、よく見ると、その子どもたちはどこかがおかしい。
すぐれたホラーというのは、必ずといっていいほど日常が秀逸に描かれている。そして、そんな日常に不穏なさざ波が立つのがトリガーとなって次第にテンポが加速し、恐怖のボルテージを高めていく。

この「イノセンツ」はそんなすぐれたホラーの空気感の装いを見事にまとって、見るものを釘付け同然に引き込んでいく。でも、そのテイストはノルウェーの空気のようにあくまでも冷え切って静かなのだ。
使い古されたものを新たな革袋に、という言葉があるけども、本作はまさにそれ。
本作はいってみれば良くあるサイキックスリラーなのだが、その切り口を少し変えるだけで新たなルックスを生み出すことに成功している稀有な例だ。
緑豊かな自然に囲まれたノルウェー郊外の高層団地。ここに、自閉症で言葉が話せない姉のアナとその妹のイーダの4人家族が引っ越してくる。そこでの最初の夏休みとなる退屈なある一日、イーダはベンという少年と出会う。ベンがイーダにいいものを見せてやると言って披露したのは、落としたビンのキャップを手を使わずに飛ばしてみせるマジックまがいの芸当だった。

本作はまず序盤の子どもたちを取り巻く日常を描くのが上手い。子供たちの演技もさることながら、子どもたちの自然な会話、子どもたちの笑顔、一挙手一投足のその仕草、それがまるでドキュメンタリーのようにリアルだ。そして、そのリアルが、サイキックな能力という切り口で、コップの中の水に小さな波紋が出来て、その波紋が次第にさざ波に変わっていくように様相が変化していくのが手に取るように感じられるところが秀逸だ。
主人公である少女イーダ、そして少年ベン。仲良くなった二人だが、ベンがいたずらに猫を殺してしまうという行為を見てからイーダはベンに不穏な脅威を感じ始める。
子供たちののどかな夏休み映画が、サイキックスリラーの様相を帯び始めるのに一役買うのが、特殊な感応能力を持った少女アイシャの登場。このアイシャにイーダの自閉症の姉のアナが感応し、共鳴するところからアナは自らも能力に覚醒していく。
これがハリウッド映画ならマーベルばりに仰々しく描かれるところだが、本作の場合、あくまでも日常の視点からさりげなく描写を重ねていくところがいい。
やがて、アナとアイシャが感応しあうことで、少しづつ言葉すら話せるようになるアナだったが、それと共にベンの小さな悪意が徐々にドス黒いものに変わり始める。
そうして、自然と生じ始める子どもたちの間での対立の構図。ベンはイーダの姉アナが自分よりも強大な能力を持っていることを悟るや、自らが持つ他人を操るという特殊な能力を駆使して更に邪悪な対立を仕掛けていく。
ここからは定石通りサイキックな能力を駆使してのバトルの構図となるが、序盤からの透明感のある映像で切り取られたリアルの余韻が大きいだけに、そのリアルが、サイキックバトルというお決まりの定石に嵌っていくのにこちらが奇妙な快感を覚えてしまうところが何とも新しい。
かくして、ベンがアイシャの母親を操ってアイシャの死という事態をもたらした時、本作の主役でもあり4人の中でただ一人能力のない傍観者だったイーダが立ちあがる。
ここまでくればマンガに馴染み深い日本人ならサイキックを扱った数々の作品を想起するだろう、一世代も二世代も古い負け犬なら「幻魔大戦」であり「童夢」であり、「アキラ」といったところだ。それがノルウェーという国から、北欧独特のテイストで目の前に現出するのを目の当たりにするのは妙な感動でもあり自然とこちらの感情もヒートアップしてくるから不思議だ。

殺されたアイシャの仇を討つため行動に出たイーダが失敗に終わり、逆に怪我を負って追い詰められた時、自閉症の姉のアナが悪の少年と化したベンの前に決然と立ちはだかる。そのラストのクライマックスたるや、大友克洋のあの傑作「童夢」を忠実に映像化したようなサプライズがある。

まるで西部劇の最後の決闘のような二人の対決。だが、そこで使われる武器は人間の思念なのだ。団地の公園というのどかなありふれた光景の中で繰り広げられる息詰まる決闘の末に訪れる結末。やがて、その激闘は、誰にも知られることもなく、再び何事もなかったようにありふれた日常の中に埋没していく。

エスパー、サイキック、テレパシー、テレキネシス、幾多の映画でそれらは誰もが目にしたはず、しかし、本作を見た時、その新鮮さに誰もが全く新しい革袋から酒を吞みほしたような気分になるのではなかろうか。
北欧の国ノルウェー産の2021年製のこのワインの味を是非、どうぞ
負け犬が人生ゲームの結末に開いた口が塞がらないほど唖然とした件「ゲーム」
映画館であまりの結末に呆然とし、ただアングリと口を開けていた記憶も鮮明な、あのデビッド・フィンチャーの不条理体感型サスペンス
(評価 76点)

映画にも二通りある。ドキュメンタリーとフィクションだ。フィクションの中でも、とりわけサスペンス、それもミステリアスなサスペンスということになれば、観客は当然、結末見たさにフィクションの世界に没入する。
ところが、その結末にも二通りあって、仰天するほど感心するか、ただ呆然と口をアングリと開けてあきれるかの二つのパターン。
「エイリアン3」を観て、その鋭い映像感覚に早くから瞠目していたデビッド・フィンチャーが自分の予見どおりに「セブン」でブレイクを果たし、嬉しさもそのままに公開当時、期待満々で劇場に駆け付けた。その時、宣伝で大々的に謳っていたのは「セブン」以上の驚愕のラスト。その惹句に釣られた観客が詰めかけた満員の劇場で負け犬は本作を鑑賞したのだった。

序盤、中盤、なるほど不条理な出だしから、フィンチャー流の尖った映像で次々、展開されるくだりには大満足で、負け犬のボルテージも上がりっぱなしだったのを覚えている。
父親譲りの資産家で、自身トレーダーのニコラス(マイケル・ダグラス)は、ある日、疎遠だった弟のコンラッド(ショーン・ペン)から、とあるゲームを提供している会社のことを知らされる。

幼少の頃、父親が自殺したトラウマに今も苛まれていたニコラスは、気晴らしも兼ねてその会社の門を叩く。そして、成り行きで、その会社が提供するゲームに参画するという契約をしてしまう。

とくれば、これはもう、負け犬も垂涎するほど大好きなトワイライト・ゾーンを彷彿とさせる不条理型サスペンス。
映画は思わせぶりなその出だしから、ニコラスに降りかかる様々なイベントに否が応にも興味をそそられる巧みな演出にもそそられ、この負け犬は釘付け状態になって、食い入るようにスクリーンを見つめていたのを覚えている。

面白いのは面白い、それも抜群にといっていい、ところがだ、途中から段々と不安になって来たのだ。
ここまで風呂敷を拡げてどうする気だ。どうやってここまで拡げた大風呂敷を畳むつもりなんだ・・?負け犬が途中から気になりだした不安感とはまさにそれ。

元々、小心者で、心配性の負け犬だ。そうやって不安感を胸に募らせている間にも映画は畳みかけるように、どんどんさらに謎を高めたままクライマッスへと突入していく。
そして、いよいよそのゲームの謎が明かされる結末の瞬間が到来したのだ。果たして、負け犬のリアクションは冒頭に提示した二通りのパターンのいずれだったのか!

・・・と、ここまで煽っておいて、それについては敢えてここでは記しません。とはいえ、映画が終わり、満員の映画館から吐き出される他の観客たちと、すごすごとロビーに向かって引き上げる負け犬の肩は消沈していたとだけ記しておこう。
そんな出来事から、数十年の時を経て、実は本作を再見した。すると、不思議なことに逆に結末を知っているからか、変な期待もせずに肩の力を抜いて、純粋にエンタメとして十分に楽しんだ。以来、まるでマエストロの匠の技を賞味するように何度も見るようになったからつくづく不思議なもの。
もしも、本作、ご覧になっていない方がいたら、体感型結末体験ゲームとして本作に心して挑んでみては如何でしょう。アングリと開いた口から感心したという言葉が発せられるか?それともアングリ開いた口もそのままにアングリーな腹立たしいことこの上ない気分になるか?これは一種のギャンブルですよ(笑)。
人生はゲーム。そして、誰の人生であってもその人生ゲームには、必ず結末が訪れる。願わくば、その結末が煽るだけ煽っておいて肩透かし、というのだけは避けたいものですよね~
負け犬がエイティーズのエログロホラーにチョット感心した件「ソサエティー」
肉体は欲にまみれて変容する、エイティーズサウンドに乗せて送るエログロボディーメタモルフォーゼホラー
(評価 70点)

エログロホラーという言葉の響き。それはホラーの中でも一つのジャンルを成していると言えるのではなかろうか。本作は、そんなエロとグロ、それを80年代のあの独特のテイストで描き出した、ちょっと珍奇で、シュールなホラーの佳作。
ハイソなコミュニティーとしてつとに有名なビバリーヒルズの豪邸で何不自由なく暮らすティーンエイジャーのビル。しかし、そんなビルも何故か、やたらと馴れ馴れしくベタベタと親密にしている妹と両親たちに違和感を覚えている。

ある日、妹の元カレに聞かされたのは、ビルの家族がオージーまがいの行為をしている声を密かに録音したテープだった。そして、たまたまビルがシャワー室で見かけたのは奇妙に上半身と下半身が捻じれた妹の肉体だった。

本作を珍奇なホラーと形容したが、このイントロから、ビルが家族や自分の周囲のコミュニティーに不信感を覚え、疑惑も顕わに、どんどんパラノイアに陥っていく姿を描く前半から中盤にかけては、あくまでもオーソドックス。
自分が属するコミュニティーが、異常な集団ではないかについてのパラノイアといえば、冷戦や全体主義の抑圧の恐怖を描く60年代や70年代によく見られたSFホラーの典型とも言える。そんな作品群で描かれた恐怖の根源は、エイリアンに精神や肉体を乗っ取られたり、洗脳されたりしたゾンビのような人々だった。
それでは、一体、本作で描かれる恐怖の根源、異様なコミュニティーの実態とは何なのか?

本作のテイストがちょっとユニークなのは、何かがおかしいという不信感に苛まれるビル。そんなビルが目撃する不審な出来事で奇妙な不協和音を奏でパラノイアのボルテージを高めていくスタイルが、パイオツ丸出しのギャルが横溢する80年代の学園もののテイストから、クライマックスにかけて一転しておぞましいことこの上ないホラーに転じていく妙味といえる。
パラノイアとなって、無理矢理、家族に救急車で担ぎ込まれたビルが救急病棟から逃げ出し、深夜、自分の豪邸に忍び込んだビルが目撃したものとは・・・!?

長寿、繁栄、富、無限の若さへの渇望、そうしたものを手にいれようと集団を成す人間たち、それを可能にするものが明かされるラスト30分の幕開けに、本作を見た人なら少しギョッとするかもしれない。
そこで繰り広げられるビジュアルを一手に担うのが、ハリウッドで活躍した日本の特殊メイクアーティストの第一人者、スクリーミング・マッド・ジョージ。オープニング・クレジットから不穏なビジュアルを垣間見せる本作で、最後に見せつける、おぞましさきわまりないドロドログチャグチャ全開のビジュアルはまさに同氏の面目躍如。それに本作ではエロが加わるから一層にそのテンションも高まる。

しかし、本作、クライマックスに至るまで見た人なら、まるでデジャブのように、このアイデアや作品全体の体裁から、何かに似てない?と思う人もいるのではなかろうか。この負け犬がまさにそうだった。
そう、近頃、やたらとよく聞く名前、ジョーダン・ピール。その監督が大ブレイクを果たした出世作「ゲットアウト」だ。

本作「ソサエティー」の監督は、やはりエログロでその筋のマニアでは有名なブライアン・ユズナだが。あくまでもB級に甘んじていた同監督は本作のアイデアに入れ込んで一発ブレイクを目論み、本作をぶち上げた。だが、ヨーロッパではそこそこの評判だったものの、本国では無視同然の扱いでフェイドアウトの末路となった。
「ソサエティー」や「ゲットアウト」、どちらのコンセプトも構成は似通ってはいるもののアイデアやクライマックスのビジュアルは「ソサエティー」の方がショック度は高い。
「ゲットアウト」の場合、監督がブラックで、公開当時、たまたま貼られた人種差別ホラーというレッテルが独り歩きして大ブレイクしたふしもある。
そういう意味では、本作自体が負け犬映画ともいえる。だからですかね~この負け犬が本作に人並み以上の愛着を持ってしまうのも。
負け犬のA級監督がヒッチコックの傑作群に他流試合を挑んだ件「パニック・ルーム」
気鋭のデビッド・フィンチャーが挑んだ限定空間サスペンスは何度見ても一気呵成に見れる良作だった
(評価 74点)

デビッド・フィンチャーのフィルモグラフィでも何故か評価が芳しくない本作。とはいえ本作、限定空間、籠城といった負け犬好みのB級感覚のテイストでグングンラストまで引っ張てくれる良作には違いない。
そもそも本作にひときわ魅力を感じるのは、敬愛するサスペンスの神様ヒッチコックに果敢に挑んでいるような心意気を感じるから。
オープニングからしてそれは明らか。ニューヨークの摩天楼の壁面にポッカリ浮かぶタイトルクレジットは、あのヒッチコックの傑作「北北西に進路を取れ」の有名なソール・バスのタイトルバックそのまま。かくして、そのオープニングから本作は単刀直入に簡潔なプロットに突入して行く。
シングルマザーのメグ(ジョディ・フォスター)と、その娘サラが借りた豪華なタウンマンション。ところが母子が入居した当日の夜中、三人組の強盗にまんまと進入される。実は、マンションにはハイソなテナントたち用に、災害避難時用の万能避難部屋パニックルームが装備されていて・・・という本作のプロットをご存じの方も多いはず。

そして、本作は、終始、そのマンションから一歩も出ることなく、その上、そのマンションの内なる密室たるパニックルームという二重の限定空間を巡って展開される。
内と外、そして外と内という限られた舞台設定。サスペンスに馴染の方なら本作を見たらすぐにヒッチコックの超傑作「裏窓」が二重映しのように被るはず。内部はパニックルームというハイテク空間ながら、外装は古風なマンションのルックスは「裏窓」の舞台になったアパートの外観にどこか瓜二つの印象もある。

強盗の襲撃を察知し、咄嗟に逃げ込んだパニックルーム。その壁越しに展開される籠城サスペンスといえば、この負け犬がもっとも偏愛する籠城サスペンスの超傑作「要塞警察」のテイストが横溢しているのも嬉しい。そもそも、強盗が押し入ったのもそのパニックルームの中に、お宝の債権が隠されていたから、というプロットは出来すぎにせよ、中盤の、強盗達が立て籠ったメグたちをいぶしだそうと、プロパンガスを送り込んで、返り討ちに会って逆襲されるくだりからの、壁を隔てての知恵比べの応酬は見ていて実に楽しくスリリング。部屋の外に置いてきた携帯を奪取しようと、メグが四苦八苦するシーンの畳みかけるような演出はフィンチャーならではのテクニックが存分に味わえて実に楽しい。

また、本編で印象的なのが、滑らかに縦横にマンションのディテイルを移動していくCGの数々。ここなど、ヒッチコックのアナログのサスペンスにフィンチャーがまるで他流試合でも挑んでいるような遊び心すら感じさせる。

終盤、内にいたはずのメグが部屋から出て、強盗達が逆にパニックルームに閉じ込められて立場が逆転するくだりは実にニンマリ。そこから急転直下、映画は終幕へと進んでいく。
大団円を思わせるラスト。アパートの外にキャメラが出て、雨風の中、強盗の懐から風で吹き飛ばされた債権の紙切れが舞い散るさまは、ヒッチコックの「裏窓」の、殺人犯がお縄になる大団円にもどこか似ている。

あ、そうそう、忘れてはならないのは、娘のサラが糖尿病で、インシュリン注射を打たなければ危ないという、夜明けまでというタイムリミットに一役買うマクガフィンの仕掛けがスパイスされているもの嬉しい。ここまで揃えばそのテイストはまさにB級映画の王道といっていい。
そうした仕掛けが、メグがパニックルームから逆に締め出されてしまうくだりで生きて来る、本作の脚本はデビッド・コープ。パニック・ルームという小道具を着想した瞬間から、プロットは結構、温めていたんではなかろうか。本作の元ネタが、屋内エレベーターに閉じ込められた老女が、進入してきた強盗たちと繰り広げる、サスペンス映画のカルトな傑作、これまた負け犬垂涎のフェイバリット「不意打ち」という説もある。現に、本作にも屋内エレベーターで右往左往するくだりがちゃんと盛り込まれている。

フィンチャーといえば、「セブン」でブレイクして以来、今に至るまで、Aランクの監督として確固たる地位を築いているが、そのフィンチャーがこじんまりとしたB級然とした籠城ものを手掛けたことがファンの反感を買ったのではないかとも今思えば思えて来る。
何はともあれ、籠城に立て籠もりに引きこもり、密室空間といった負け犬好みの趣味をお持ちの方なら一見に値する作品であることは確か。
よろしければ、文中でも触れた「裏窓」は勿論、「要塞警察」「不意打ち」といった作品もテイストいただくのは如何でしょうか?きっと密やかな悦楽に浸れると思いますよ